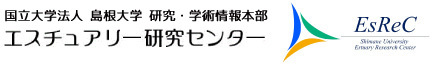南大東島の湖沼調査を実施しました
公開日 2025年04月28日


文責:香月興太
2025年4月16日から23日にかけて沖縄県の南大東島を訪問し、エスチュアリー研究センターの瀬戸先生および教育学部の辻本先生と共に湖沼堆積物調査を実施しました。南大東島は沖縄本島から東に約360 km離れた離島であり、サンゴ礁の隆起によってできた隆起環礁の島です。南大東島は縁辺部で標高が高く中央部で標高が低いお椀状の形状をしており、中央には複数の湖沼が存在しています。これらの湖沼はドリーネ湖であり、底部から海水の染み込みが発生した結果、純粋な淡水湖ではなくその多くは汽水湖となっています。
今回の調査では、南大東島湖沼が湖底堆積物に埋蔵する炭素量の変遷を把握し、炭素埋蔵量に関わる基礎生産者を明らかにするために、湖内で水質調査および柱状堆積物の採泥調査を行いました。図1は調査湖沼の内の一つ、月見池です。南大東島の湖沼は湖岸に亜熱帯性の植物群が繁茂しており、浅い湖では湖底にも水草が繁茂していることが確認できます。

図1.南大東島南部に位置する月見池
南大東島の湖沼群の多くは大正時代に掘削されたとされる水路によってつながっています(図2)。水路は現在でもボートで行き来できるような場所もあれば、浅く水生植物が繁茂している場所や外来種と思しき水草が大量繁茂している個所もありました。湖沼の多くは水路でつながっているにも関わらず湖沼ごとの塩分には大きな差異があるようです。

図2.湖沼を繋ぐ連絡水路 奥に見えるのは鴨池
図3は月見池の湖盆から採取した湖底堆積物で、有機質な軟泥が堆積していました。堆積層は2か所の乳白色の縞状堆積物を境界に3層に区分されており、おそらく入植開始以前の環境下から開拓や水路工事の影響を受けて変化した環境の変化を記録していると考えられ、今後の調査で水環境と基礎生態系の変遷が明らかとなることが期待されます。

図3.不擾乱半割採泥器によって月見池湖底から採取された堆積物
今回の調査に当たって南大東島村役場産業課の仲田課長には大変お世話になりました。また、南大東村教育委員会の沖山さん、村役場土木課の仲田さん、沖縄県農林水産部の眞榮平さん、ネイチャーガイドの東さんには突然の連絡にも関わらず親切に対応していただきました。ありがとうございました。