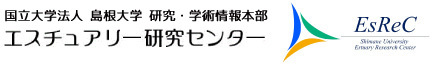第164回汽水域懇談会 -長塚さら沙 氏-【02/20開催】
公開日 2025年01月16日

第164回の懇談会は長塚さら沙 氏(東京海洋大学 大学院海洋科学技術研究科)の話題提供で行います。皆様のご参加をお待ちしております。
164回汽水域懇談会(日程のポスター)
第164回汽水域懇談会
題目 :小笠原諸島に分布するミズクラゲ属の系統分類
話題提供者 : 長塚さら沙 (東京海洋大学 大学院海洋科学技術研究科)
日時:2025年 2月20日(木)10:00–11:00
場所:ハイブリッド開催(センター2階セミナー室(201号室)とZoom を併用)
申込み方法:アンケートシステムにご登録ください(2月18日(火)正午 締切)
【講演概要】
小笠原諸島は東京から約1000km南に位置しており、約4800万年前に誕生して以来一度も陸続きになったことのない海洋島である。小笠原諸島父島の二見湾では、ミズクラゲ属の一種であるナンヨウミズクラゲの出現が報告されている。ミズクラゲ属は世界各地に分布するプランクトンであり、しばしば大量に発生し、海洋生態系や人間活動に及ぼす影響が大きい生物であると考えられている。特に、小笠原諸島は世界自然遺産に登録され固有種が多く分布していることから、本諸島内におけるナンヨウミズクラゲ(Aurelia malayensis)の分布や生態を明らかにすることは環境保全や島嶼生態系の今後を考える際に重要であると考えられる。しかし、小笠原諸島における生物の生態研究は陸域が中心となっており、海域に関する知見は乏しいのが現状であった。
本講演では、ナンヨウミズクラゲと小笠原諸島の海洋生態系との相互作用に触れながら、本州沿岸に分布するミズクラゲ属とナンヨウミズクラゲとの違い、ナンヨウミズクラゲに気候変動や人為的影響が今後どのように影響を与えるか等を説明する。