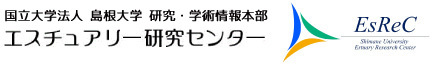第168回汽水域懇談会 -梶田展人 博士/有田壱成 氏-【11/27開催】
公開日 2025年11月07日


第168回の懇談会は梶田展人 博士(弘前大学)と有田壱成 氏 (弘前大学)の話題提供で行います。皆様のご参加をお待ちしております。
168回汽水域懇談会(日程のポスター)
第168回汽水域懇談会
日時:2025年 11月27日(木)15:00–16:00
場所:ハイブリッド開催(センター2階セミナー室(201号室)とZoom を併用)
申込み方法:アンケートシステムにご登録ください(11月25日(火)正午 締切)
題目 1:東南極丸湾大池の離水過程と氷床変動史の復元
話題提供者 : 有田壱成 (弘前大学 理工学研究科 地球環境防災学コース 修士一年)
【講演概要】
東南極沿岸域には、氷床の後退に伴って隆起した地形上に多数の湖沼が形成されている。これらの湖沼堆積物は、氷床変動に伴う環境変化を高解像度で記録するアーカイブとして注目されている。本研究では、宗谷海岸の丸湾大池に着目し、氷河に近接する東部湖盆から採取した堆積物コアを対象に、混濁水分析や蛍光X線分析(XRF)など複数の手法を用いて、湖沼環境の変遷を復元した。その結果、約4,000年前の離水以降に一時的な海洋再接続期が存在し、その際に物理的なイベントを伴った可能性が示唆される。これらの知見は、中期完新世以降の氷床変動史を制約する上で新たな手がかりとなり得る。今後は、珪藻群集解析を加えることで、より精緻な古環境復元を進めていく予定である。
題目 2:青森県鷹架沼におけるアルケノン古水温復元の展望
話題提供者 : 梶田展人 (弘前大学 理工学研究科 地球環境防災学コース)
【講演概要】
ハプト藻が合成する長鎖アルキルケトン化合物(アルケノン)は、その二重結合の相対的な個数(不飽和度)が棲息水温と比例して変化する。海洋には円石藻と分類されるアルケノン生産種が広く分布し、過去の海水温を復元するツールとして広く用いられてきた。本研究では、青森県鷹架沼の湖底堆積物からアルケノンを発見し、環境DNA解析によって、海洋種とは異なる2種の汽水生ハプト藻が生息していることを突き止めた。鷹架沼生息種と遺伝的に近い種から報告されたアルケノン不飽和度と温度の換算式を適用することで、鷹架沼の湖沼堆積物から過去の湖水温を復元できることが示唆された。今後、鷹架沼で長尺の湖底堆積物を掘削し、縄文時代の気候復元を行うことを目指す。