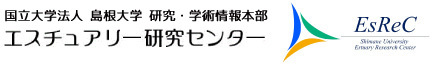第169回汽水域懇談会 -仲村康秀 博士/長塚さら沙 博士-【12/3開催】
公開日 2025年11月19日


第169回の懇談会は仲村康秀 博士(島根大学 エスチュアリー研究センター 助教)と長塚さら沙 博士 (島根大学 エスチュアリー研究センター 研究員)の話題提供で行います。皆様のご参加をお待ちしております。
169回汽水域懇談会(日程のポスター)
第169回汽水域懇談会
日時:2025年 12月3日(水)15:30–16:30
場所:ハイブリッド開催(センター2階セミナー室(201号室)とZoom を併用)
申込み方法:アンケートシステムにご登録ください(12月2日(火)正午 締切)
題目 1:プランクトンに着目したDNAメタバーコーディング:島根県中海における過去5000年間の環境・生態系変化
話題提供者 :長塚さら沙 博士 (島根大学エスチュアリー研究センター 研究員)
【講演概要】
地球温暖化が原因と思われる気温上昇とそれに伴う生態系構造の変化は確実に進行しており、その対策と生態系構造の経時的なモニタリングは喫緊の課題である。日本列島でも約9000–6000年前にも温暖化していた時期(いわゆる縄文海進)が知られており、地域によっては平均気温が現在より2–3度高かったと推定されている。この時期の生態系構造を高精度で解明できれば、温暖化の進行により今後の生態系がどのように変化していくのかを推定するための実証データが得られ、温暖化対策に必要な知見を提供できると考えられる。以上のような背景を踏まえ、過去の水圏生態系構造を解明するための第1歩として、本研究ではプランクトン群集を網羅的に検出できるDNAメタバーコーディング(DNA-MB)という技術を用いて、島根県中海における過去約5000年間の環境・生態系群集組成の解明を試みた。
2023年8月に中海から長さ4.65 mの堆積物コアを採取し、18S rDNA (V9) 領域を標的としたDNA-MBに供して、検出された真核生物、特にプランクトンの分類群組成を明らかにした。また、放射性炭素年代推定と、元素分析および貝形虫類の化石分析なども行った。
化学分析と貝形虫類の化石分析の結果、約1200年前に相当する層で生物組成が大きく変化することが明らかとなった。またDNA-MBの結果、約1200年前の層を境に生物組成が大きく変化する事が判明した。これらの変化は、中海が内湾環境から汽水環境に変化したことに因るものと考えられた。また、約4200年前に相当する最下層のコアからもDNAが検出することができた。本研究により、汽水域においてもDNA-MBを用いた過去の環境・生態系の推定は十分に可能であることが示された。
題目 2:プランクトンに着目したDNAメタバーコーディング:島根県宍道湖における過去10000年間の環境・生態系変化
話題提供者 :仲村康秀 博士(島根大学 エスチュアリー研究センター 助教)
【講演概要】
過去に塩分などの環境が大きく変化したことが分かっている宍道湖においても、堆積物コアに含まれるプランクトンに対してDNA-MBを用いる事で、過去の環境・生態系変化を従来より詳細に推定できると考えられる。演者らのチームは2021年に宍道湖から得られた堆積物コアから、過去約2500年分の環境・生態系変化を解明する事に成功しているため、同地域でさらに過去の情報を得ることを試みた。
2022年1月に過去に宍道湖の一部であった出雲平野(現在は陸地となっている場所)から、長さ約34 mの堆積物コアを採取し、上述の中海の研究と同様の手法で分析を行った。
結果として、この地域では過去1万年間に微塩分から高塩分まで環境が大きく変化し、それに合わせて4つの生態系構造に区分できることが明らかとなった。また、このように塩分が大きく変わるエスチュアリーにおいても、DNA-MBを用いた過去の環境・生態系の推定は1万年前まで十分実用可能であることが示された。